糖尿病は「血糖値が高くなる病気」として知られていますが、実際にはどのような病気なのでしょうか? この記事では、医療関係者でなくても理解できるように、糖尿病の基本から種類・原因・症状・治療法までをわかりやすく紹介します。
糖尿病とは?
糖尿病(とうにょうびょう)とは、一言でいうと「血糖値(けっとうち)が慢性的に高い状態が続く病気」のことです。 血糖値とは、血液の中に含まれるブドウ糖(=糖分)の濃度のこと。この値が正常な範囲を超えて高くなってしまうと、体にさまざまな悪影響が出てきます。
インスリンの役割とは?血糖値との関係
インスリンは、すい臓(膵臓)から分泌されるホルモンで、食事でとった糖分をエネルギーとして体に取り込む役割をしています。 このインスリンがうまく働かない、または十分に出ないと、血液中の糖分が体に吸収されずに血液中に残ってしまい、血糖値が高くなってしまうのです。
糖尿病は“静かに進行する”病気
糖尿病は、初期のうちはあまり自覚症状がありません。 そのため、「気づいたときにはかなり進行していた」というケースも少なくありません。 進行すると、目・腎臓・神経などに合併症が出てしまうこともあるため、早期の発見と対応がとても大切です。
糖尿病の原因となる“慢性的な高血糖”とは?
糖尿病は「血糖値が高い病気」と言われますが、ポイントは一時的にではなく、“慢性的に”高いということです。
たとえば、甘いものを食べたあとなどは、誰でも一時的に血糖値が上がります。 しかし、健康な人なら、インスリンの働きで1~2時間ほどで元の正常値に戻ります。
ところが糖尿病では、インスリンが足りない or 働きが悪いために、 食後だけでなく空腹時でも血糖値が高い状態が続いてしまいます。
血糖値の基準と糖尿病の診断ライン
| 測定タイミング | 正常値 | 糖尿病の可能性 |
|---|---|---|
| 空腹時血糖値 | 70~99 mg/dL | 126 mg/dL以上 |
| 食後2時間 | ~140 mg/dL | 200 mg/dL以上 |
| HbA1c | ~5.6% | 6.5%以上 |
※HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)は、過去1〜2か月間の血糖値の平均を表す数値です。
血糖値が長期間にわたって高い状態のことを「慢性的な高血糖」と呼びます。 これが続くことで、体のあちこちに悪影響が出てしまうのが、糖尿病の怖いところです。
詳しくは 日本糖尿病協会の解説 も参考にしてみてください。
糖尿病の主な原因と種類
1型糖尿病の原因:自己免疫の異常
自己免疫反応により、膵臓のインスリンを作る細胞(β細胞)が破壊されることで発症します。 小児~若年層に多いですが、大人での発症もあります。 発症後はインスリン注射が必要となります。
2型糖尿病の原因:生活習慣と遺伝
日本人の9割以上がこのタイプ。
- 食べ過ぎ・運動不足
- 肥満(特に内臓脂肪型)
- 家族歴(遺伝)
- 加齢
インスリンが出ていても効きにくく(インスリン抵抗性)、次第に膵臓が疲れてインスリン分泌も減少していきます。
その他の要因による糖尿病
- 強いストレス
- 加齢による機能低下
- 薬(ステロイド・抗精神病薬など)
- 他の病気(膵炎やホルモン異常など)
糖尿病は「甘いものを食べすぎたから」だけが原因ではありません。 体質・免疫・ストレス・年齢など、さまざまな要因が関わっている病気です。
🔗 あわせて読みたい関連記事
⚠ 自己診断は禁物!不安を感じたら早めに受診を
糖尿病かもしれないと感じても、ネット情報だけで自己判断せず、必ず医療機関で検査を受けましょう。 特に以下の症状がある場合は早期受診をおすすめします:
- のどが異常に渇く
- 急に体重が減った
- 体がだるく、疲れやすい
- 尿の回数や量が増えた
※ちなみに私は1か月の間にこの症状がすべてでました。
🔚 まとめ:糖尿病は“知って備える”ことで怖くない
糖尿病は生活に影響を与える病気ですが、早期の発見と正しい管理ができれば、コントロールしながら暮らすことができます。
このブログでは、検査入院や治療の体験談も記録しているので、気になる方はあわせて読んでみてくださいね。
糖尿病の肩の食事の選び方はこちら↓
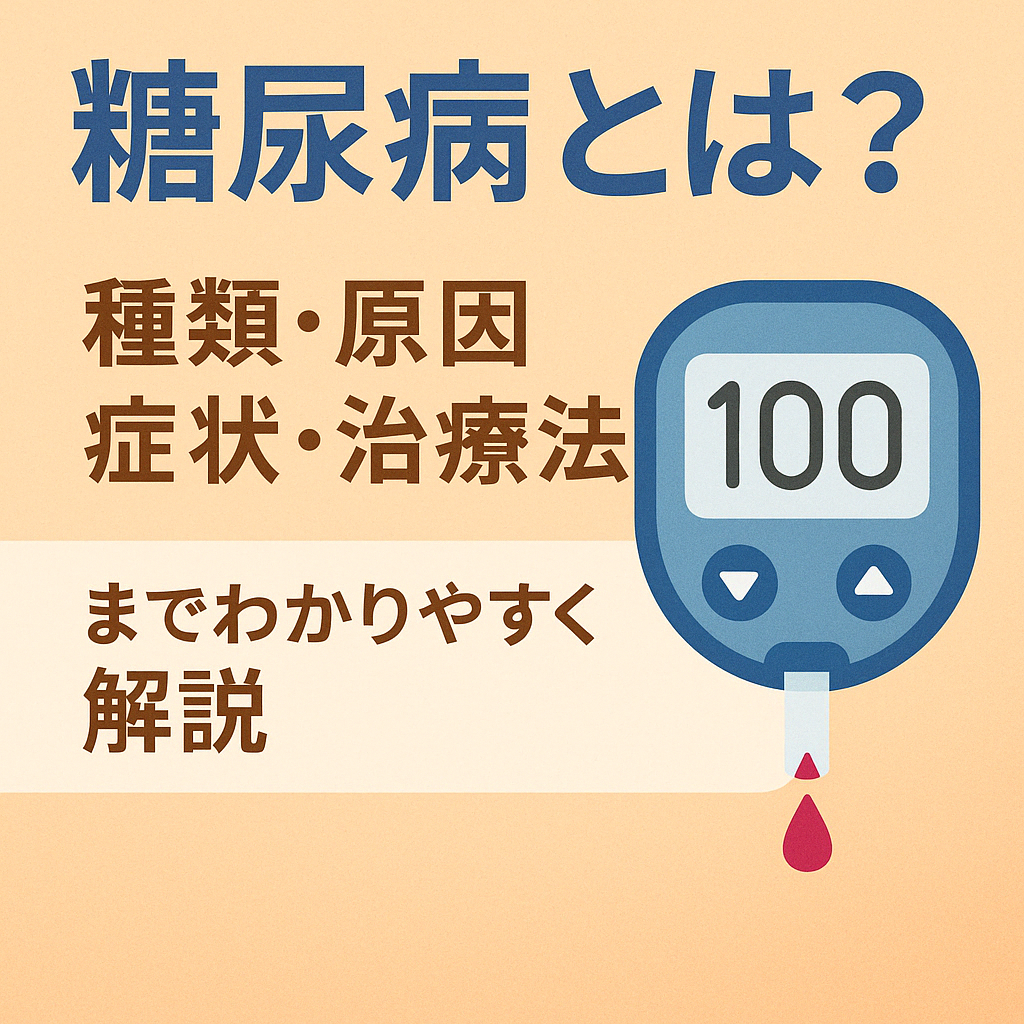
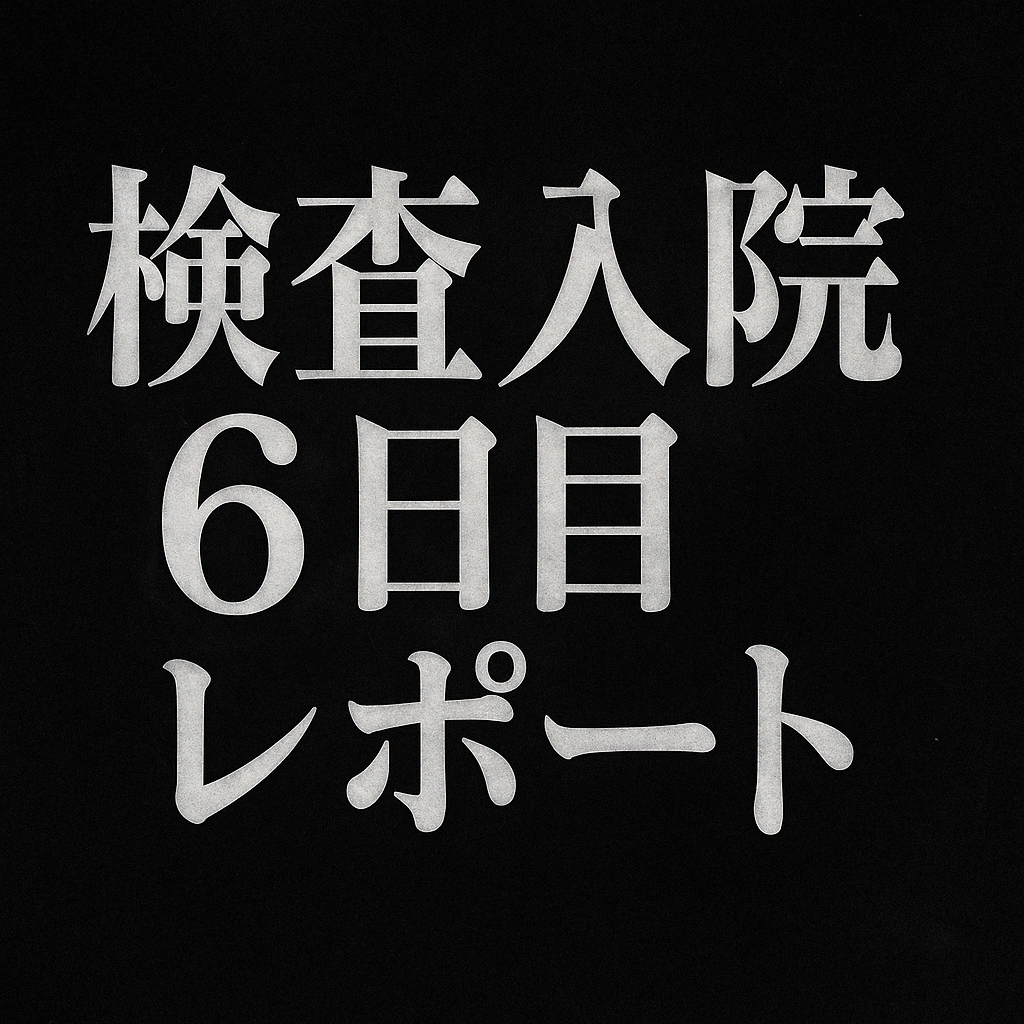
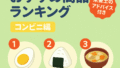
コメント